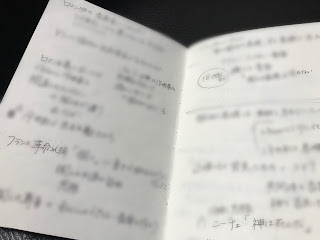今回のテーマは『ピアノのロマン主義』。
講師は岡田暁生先生。
一番後ろの席で、ノートにびっしりメモしました。
講義の覚え書き。
まず「ロマン主義」とは。
ロマンと言われるくらいですから、19世紀はロマンチックな時代だったのかと言うと、そうではなく、世界からロマンチックがどんどん消えていく時代。
科学の発展により、いろんな物が機械化、工業化され、味気なくなっていきます。
そして、資本主義、植民地…全くロマンチックな時代ではないからこそ、音楽にロマンを求めました。
ロマン主義を代表する作曲家は誰?
ロマン主義の作曲家は大勢いますが、1人ひとり個性が強く作風はバラバラです。
誰をロマン主義の代表とするか、1人だけを挙げるのは、無理な話です。
なぜ個性の百花繚乱となったのか。
フランス革命以降、個人の自由(内面、思想の自由)が尊重されるようになりました。
個人が尊重されるようになると、自分にしかできない音楽を作ろうと思うようになります。
18世紀までの、求められて作る音楽、職人の音楽ではなく、個性を表現する意識が芽生えます。
「個性」は「孤独」と結びつきます。
ニーチェの「神は死んだ」という有名な言葉がありますが、神を否定し、共同体を否定した結果、人間は孤独になります。
19世紀からずっと、孤独は人生の課題であり続けています。
共同体の絆を作りたい、繋がりたいという欲求が生まれ、その手段が音楽でした。
ちなみに、19世紀は音楽、20世紀には映画やスポーツ、21世紀の今はインターネットがつながる手段です。
孤独から疎外感を感じます。
そして、私が今いるこの場所は私の本当の居場所ではない、ユートピア(楽園)がどこかにあるはずだ、と、自分探しの旅が始まります。
神を信じていた時代には「天国」という居場所がありました。
結局、ユートピアなんていうのはどこにもなく、生まれる失望感…
フランス系ポーランド人のショパンは、ポーランド(スラブ系)にいれば自分の中のフランスを意識し、フランスに行けば祖国のポーランドを意識します。
自分の中での「自分のずれ」です。
いろんな書籍で、ショパンは生涯、生まれ故郷のポーランドを心の中に持っていた(故郷想いな作曲家)と書かれています。
その部分を、岡田先生は、こうおっしゃいます。
フランスにいながらポーランドのことを心配する、でも頑なにポーランドへ帰ろうとはしない、帰れば良いのに、でも帰らずして想う、それがショパンのロマンチズム。
手に入らないことへの憧れだそうです。
シューマンは、クララとの交際を禁じられていた期間には、クララに弾いて欲しくてピアノ曲ばかりを作りますが、交際を許されるとパッタリとピアノ曲を書くのを辞めます。
夢が実現すると、興味をなくすのです。
また、フリーランスとなった作曲家は、社会から逸脱します。
安定した給与のために我慢しながら雇われ人として働く社会一般は、作曲家からは偽善のかたまりに見えたようです。
作曲家たちの個性の誇示は徐々に過激になり、気が狂った自分をあえて世間に見せつけるようになります。
ロマン主義の音楽は、想像以上に挑発的で前衛的です。
前衛的な音楽は聞きにくく受け入れ難い、でも誰にも理解してもらえないのは困る、だから曲の中に受け入れられ易いベタな美しい旋律を置きます。
ショパンの「別れの曲」はその典型で、有名な美しいメロディに挟まれた中間部は、狂気に満ちています。
講義の後、ピアノの演奏でした。
ロマン主義の作曲家の作品を1つずつ。
作曲家によって作風は全く違うけれど、その根底にある精神は同じ。
「ロマン主義」と一括りにされることにしっくりきました。
美しい旋律や心情の描写だけを見て、ロマン主義というのが、なんと薄っぺらいものか。
勉強… 勉強…